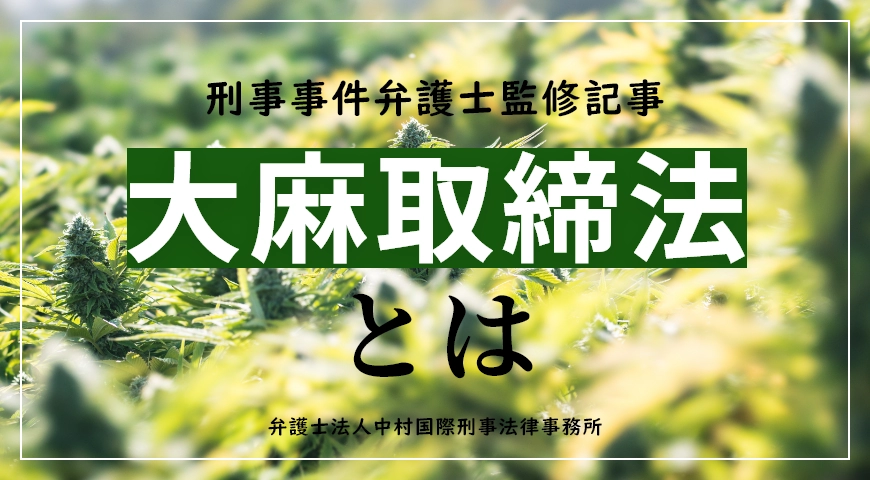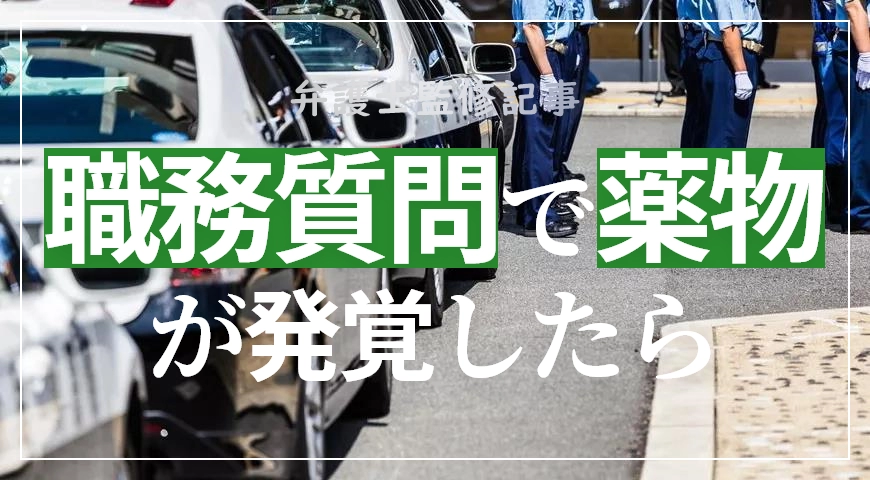昨今危険ドラッグ等の薬物が原因の交通事故が問題視されています。
危険ドラッグ等の薬物の使用した状態での自動車やバイクなどの運転はどのような罪に問われるのか疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は薬物使用に伴う交通事故について弁護士・坂本一誠が解説します。
薬物使用で運転した場合に該当する罪名や処分
危険ドラッグ等を使用して自動車等を運転した場合、死傷結果の発生の有無に関わらず道路交通法第66条違反として処罰される可能性があります。道路交通法第66条は、薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない旨規定されています。
道路交通法第66条に違反すると以下のような罰則に処されます。
まず、①麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤または毒物及び劇物取締法第3条の3に規定する政令で定められたもの(トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤を指します。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料。毒物及び劇物取締法施行令第32条の2参照)を使用した場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の2第1項第3号)。そして、②上記以外の危険ドラッグを使用した場合も過労運転等の禁止にあたるとして、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の2の2第7号)。
なお、違反行為と認定されることで、次のような行政処分を受けることがあります。まず、上記①に該当する危険ドラッグを使用して運転した場合、35点の基礎点数の付加および3年の欠格期間(免許取り消し)の行政処分を受けることとなります。そして、上記②に該当する場合、25点の基礎点数の付加および2年の欠格期間の行政処分を受けることとなります。
交通事故が起きた場合に該当する罪名
薬物を使用した状態で交通事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪及び各薬物の使用罪が成立する可能性があります。
危険運転致死傷罪とは自動車の運転により人を死傷させる行為等処罰に関する法律第2条を指し、薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で負傷させたものは15年以下の懲役、死亡させたものは1年以上の有期懲役に処されます。
薬物使用の交通事故で逮捕されたら
危険ドラッグ等の使用による交通事故を起こした場合、上記の通り危険運転致死傷等罪が成立する可能性があります。重大な犯罪ですので、逮捕・勾留の可能性が必然的に高くなります。逮捕直後の72時間は家族であっても一般的に面会することは困難です。勾留後も、接見等禁止決定が付された場合には面会できません。
一方で弁護士であれば面会の制限はありません。逮捕直後から本人と面会し、今後の見通しを伝え、取調べに対する対応について助言ができます。これにより、逮捕されたご本人が、精神的不安や動揺などから取調べで不利益な供述をしてしまい、その供述がその後の刑事訴訟で不利に働いてしまう事態を回避できます。違法な取調べに対して、取調べの問題点について熟知している弁護士が直ちに抗議して、警察の威迫や不当な誘導によって獲得された供述が不利な影響を及ぼすことを防ぐこともできます。
接見と呼ばれる弁護士による面会では、捜査官の立会いや日時の制限なく被疑者と話すことができるので、今後の対応の方向性やご家族との連絡事項について、綿密に意思疎通を取ることが可能です。さらに、検察官や裁判官に対して、ご家族が監督できる状況にあることなどから、逃亡や罪証隠滅の可能性が乏しいことを示して早期釈放を働きかけることもできます。同時に、被害者への謝罪や被害弁償や示談交渉も速やかに行います。
行政処分も受ける可能性がある
危険運転過失致死傷に該当する場合、逮捕の可能性があるだけでなく、数年に及ぶ運転免許の取消等重い行政処分を受けることがあります(道路交通法施行令別表第2)。
具体的には、危険運転致傷罪の行為に該当する場合のうち、(i)治療期間15日未満の場合には45点の基礎点数の付加および5年の欠格期間、(ii)治療期間15日ないし29日の場合には48点の基礎点数の付加および5年の欠格期間、(iii)治療期間30日ないし3ヶ月未満の場合は51点の基礎点数の付加および6年の欠格期間、(iv)治療期間3ヶ月以上または後遺障害が発生した場合には55点の基礎点数の付加および7年の欠格期間という行政処分を受けます。そして、危険運転致死罪の場合は62点の基礎点数の付加および8年の欠格期間という行政処分を受けることとなります。なお、これらの行政処分は前歴の有無に関係なく付与されるものとなります。
起訴された場合の弁護活動
被疑者が逮捕・勾留されている事件の場合には、検察官は、最大20日間の勾留期間満了までに、被疑者を起訴にするか不起訴にして釈放するかの判断をしなければなりません。不起訴となれば、前科なしに事件が終了します。一方で、起訴されると約99%の確率で有罪になってしまいます。
ですから起訴された場合には、刑事裁判に精通した弁護士が、検察官が幅広く証拠開示を受けて証拠を検討し、無罪を主張することができる事案か、それとも公訴事実を認めてできるだけ軽い量刑を狙うべき事件かを依頼者ともよく話し合って検討する必要があります。有罪となってしまう場合であっても、被害者との示談交渉や、再犯防止策を講じるなどの弁護活動の結果、実刑を回避し、執行猶予判決を獲得できれば、薬物の治療などに注力することができ、社会復帰が可能です。
起訴には、略式起訴と正式起訴の2種類があります。略式起訴は、書面審査により有罪判決を下して被告人に罰金刑を支払わせる簡易な手続により行われます。正式裁判は、公開の法廷により裁判が行われます。
判例から見る量刑
実際に起こった事件(判例)ではどのような判決が下されているのか見てみましょう。
①2014年1月、香川県善通寺市内の県道で危険ドラッグ吸引後に軽乗用車を運転し、下校中の小学生をはねる事故を起こしたとして危険運転致死傷罪に問われた男に対する裁判員裁判の判決公判があり、高松地方裁判所にて懲役12年の実刑判決が命じられています。
②2006年8月、覚醒剤の使用後に車を運転し、対向車線への逸脱事故を起こして3人を死傷させたとして、危険運転致死傷罪や覚醒剤取締法違反などの罪に問われた男に対する判決公判が2007年6月に札幌地裁で行われ、懲役22年の実刑が命じられています。
両裁判例は、被告人が「事故当時は薬物中毒・使用による酩酊状態」であったことや、薬物を使用した上での運転の危険性を承知の上で運転しており、結果他人の命を奪ったとしたことが悪質と判断され、重い実刑判決が下されている点が共通しています。
一方で、③2007年2月、覚醒剤を使用後に酩酊状態で乗用車を運転したとして、覚醒剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われていた男に対する判決公判が大阪地裁で開かれ、裁判所は男に対して執行猶予付きの有罪判決を命じているのもあります。
①、②と③の事例では、やはり他人の命を奪ったかどうかという点で大きな違いがあります。③の事例は、酩酊状態で運転をした事例ではありませんが、交通事故により他人にケガをさせたり命を奪ったりした事例ではありませんので、一般的な前科のない被告人による覚醒剤の所持・使用の事案と同様に執行猶予付きの判決が下されたものと考えられます。
まとめ
違法薬物を使用した状態での交通事故事件は、一般的な交通事故事件と比べても更に事故態様の悪質さや危険性が増す傾向にあり、罪に問われた場合には重い刑事処分に至ってしまう可能性があります。
薬物事犯、交通事犯の両方を熟知した弁護士が迅速に対応することで、より良い結果に繋がる可能性があるともいえます。
薬物による事故等の事件でお困りの場合には、不起訴処分など多くの解決実績を有する当事務所までご相談ください。