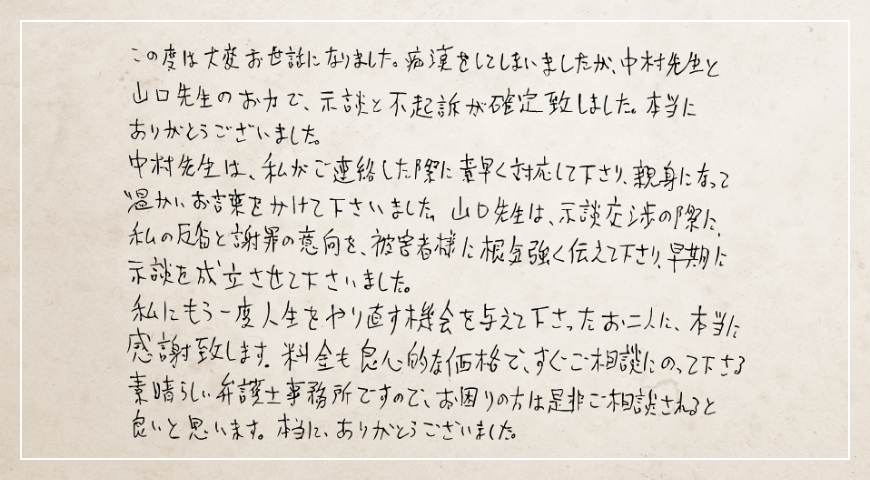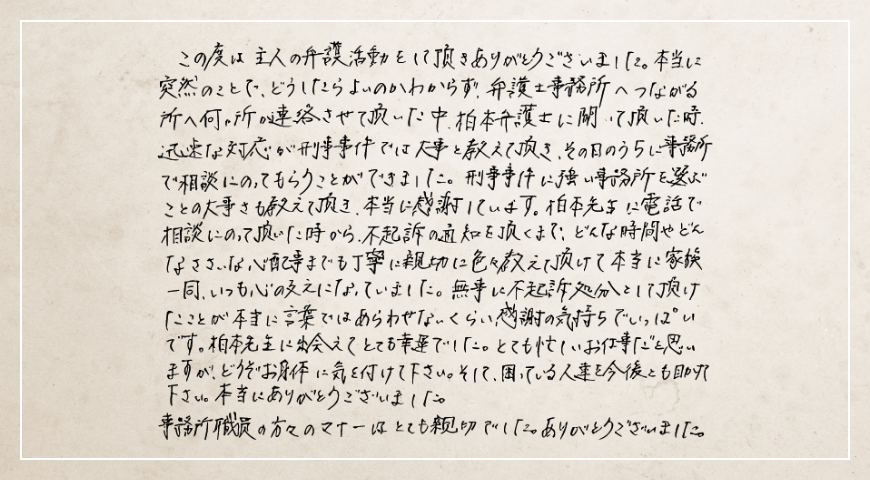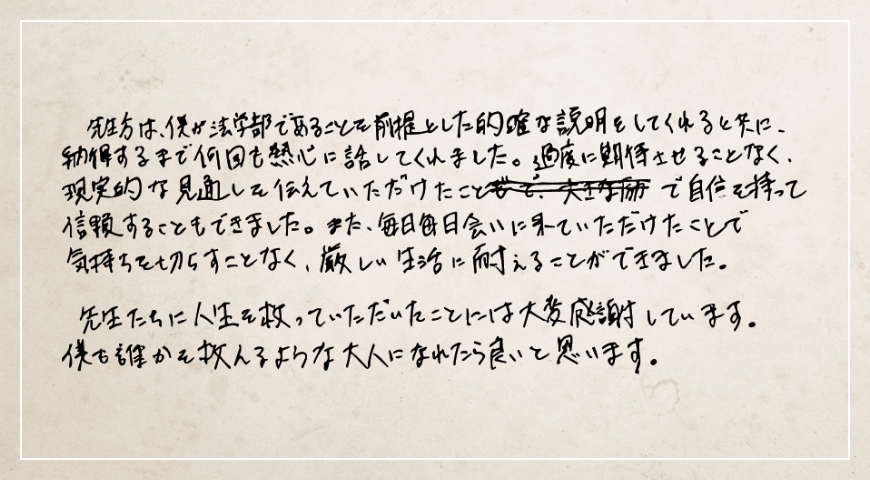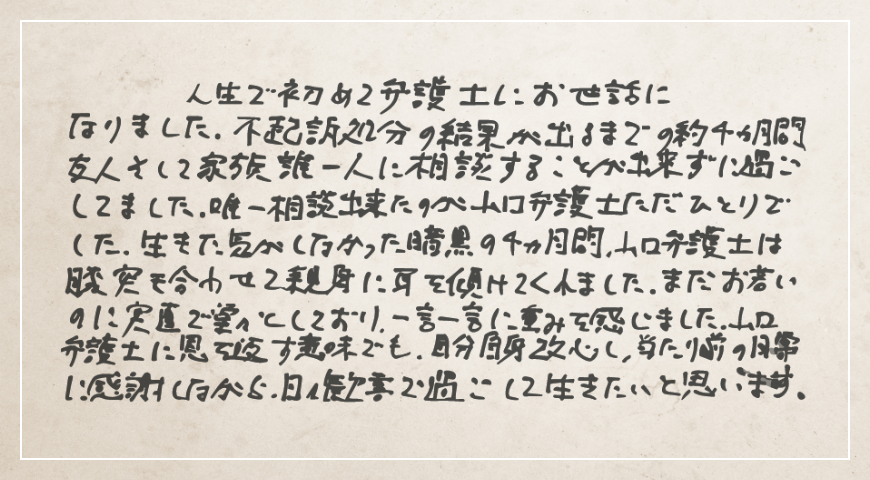被害弁償と検察側の余罪立証に対する徹底的な対抗により、執行猶予を獲得
建設会社に勤める依頼者が、下請会社の担当者と共謀して架空工事を発注し、キックバッグを得ていたとして詐欺の疑いで逮捕された事例です。
被害会社は約6億円の被害金額を主張していました。
複数年に渡って架空工事の発注が何度も行われていたため、捜査機関はそれぞれの工事につき詐欺で再逮捕を繰り返すものと思われましたが、検察庁の判断により起訴された事案の被害金額は被害会社の主張する金額のうち約1億円にとどまり、依頼者は下請会社の共犯者とともに起訴されました。
弁護人は共犯者の代理人弁護士と協議し、それぞれが分担して起訴金額の約1億円全額を弁済することができましたが、起訴金額だけでも巨額のうえ、被害会社はこれをはるかに上回る被害金額を主張していましたから、実刑判決の可能性が高い事案でした。
弁護活動
公判で検察官は、被害会社が余罪を主張していることや、我々の依頼者が下請会社よりも上の立場にあったことを立証しようとし、共犯者よりも責任が重いことを主張しようとしました。これに対し、弁護人が検察官の請求証拠に対する証拠意見を厳密に検討し、余罪の詳細な情報が記載された証拠については不同意の意見を述べ、被告人質問においても検察官が余罪の詳細な金額に立ち入った質問をした場合には異議を出して、余罪の詳細な情報が法廷に顕出されることを徹底的に防ぎました。
検察官は、被害額の重さや被告人の役割の重要性を強調して懲役6年を求刑しましたが、弁護人は弁論であくまで公判審理の対象が起訴金額であって全額弁済がされてること、犯行を主導したのは実質的には下請会社の共犯者であることを理由に執行猶予付きの判決を主張し、結果的に懲役3年執行猶予5年の判決を獲得することができました。
事件のポイント
財産犯、特に詐欺、或いは会社犯罪としての横領、背任などには長期間にわたって同種犯行を繰り返す類型が多いです。密行的に行われるため発覚が遅れるのが要因ですが、それだけに被害額も巨額にのぼります。
もっとも長期間の犯行のうち、当初の古い犯行は数年経っていることから証拠が散逸していることもあって、検事は新しいものから捜査して起訴し、その後、再逮捕を繰り返して遡って古い犯行に狙いを定め、順次起訴していきます。捜査終結に一年以上かかることもあり、結果として起訴にかかる対象被害額も大きくなるのです。
それでも、被害会社が主張する告訴額には届きません。この「余罪」に関しては、検事は証拠関係が希薄で有罪立証の確証がないことや、いつまでも捜査を続けるのは訴訟経済に反するといった理由で、起訴を諦め、代わりに悪情状としての「余罪」と位置付けて証拠請求するのです。
しかし、これは起訴していない事実を、情状事実に姿を変えさせ、実質的に処罰するもので、不告不理の原則、証拠裁判主義の原則に反するのです。
本件では、この余罪に関する検事の追及に真っ向から立ち向かい、阻止し、防御し切った成功事例です。熱心さに欠ける弁護士が担当していたら検察官の言うがままに余罪に関する証拠に対し無批判に同意し、シャンシャンで裁判を終わらせ、そして実刑判決という結果になったことでしょう。弁護士を誰にするかによって結論が左右されるのは、民事事件ではなくむしろ刑事事件なのです。
執筆者: 代表弁護士 中村勉