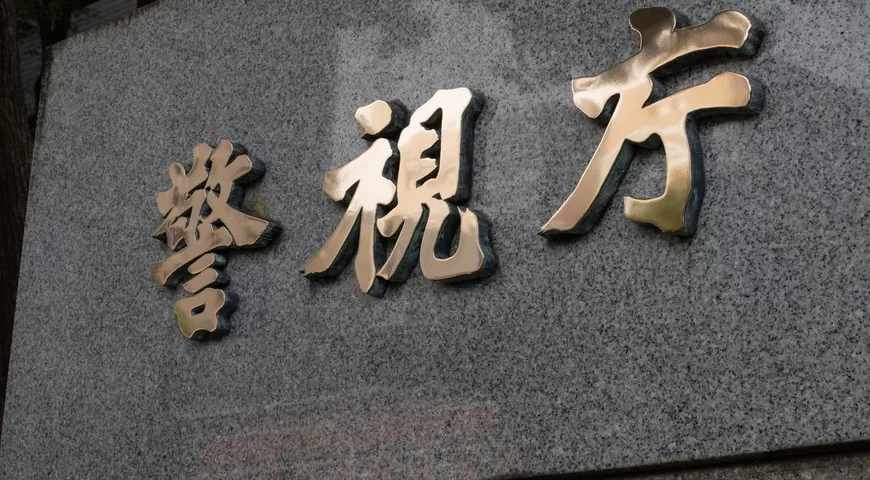身柄事件で耳にすることの多い「準抗告」。
ある日突然、裁判所から電話が入り、ご家族が10日間勾留されることが決定した旨の通知を受けた方が弁護士に相談すると、弁護士からこの言葉が出てくるかもしれません。準抗告とは何か、以下、代表弁護士・中村勉が解説します。
準抗告とは
準抗告とは裁判官が下した判断に納得できないときに、裁判所に対してその判断の取り消しや変更を求める申立て手続きです。
裁判官1名が下した判断に対して準抗告を行うと、この判断を下した裁判官を含まない別の裁判官が3名選ばれ、合議で新たな判断を下すことになります。
準抗告は原則、第1回公判期日の前に裁判官が行った処分に対する不服申し立てのことをいいます。第1回公判期日の後の不服申し立ては抗告手続きといいます。なお、検察官等が行った接見指定の処分及び押収・押収物の還付に関する処分について裁判所に対して行う不服申立ても準抗告です(刑事訴訟法第430条)。
準抗告が可能な要件
では、準抗告をすることができる裁判について解説いたします。準抗告が認められている裁判に関しては、刑事訴訟法第429条1項に定められています。
刑事訴訟法第429条1項
裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取り消しまたは変更を請求することができる。
一 忌避の申し立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受けるものに対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
1. 忌避の申し立てを却下する裁判
担当の裁判官が事件の関係者あるいはその親族である等、裁判をするにふさわしくない事情がある場合に、担当裁判官を変更してもらうよう求める申立てをしたが却下となった場合に準抗告ができます。
2. 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
準抗告というと勾留及び保釈に関する裁判に対して行われることが多いです。勾留決定や保釈却下といった身柄拘束に関する準抗告や、押収物や押収されたものに関しての準抗告が可能です。
3. 鑑定のための留置を命ずる裁判
被疑者や被告人の責任能力に問題があるような事案では、医師の精神鑑定等を集中的にさせるために病院や拘置所に一定期間収容する申立てをすることができます。その決定に対し準抗告をすることができます。
4. 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に関して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
証人等が期日に出廷しない場合に、裁判官が10万円以下の過料や費用の賠償を命じられることがあります。その命令に対しての準抗告が可能です。
5. 身体の検査を受けるものに対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
身体検査を拒んだ場合に10万円以下の過料や費用の賠償を命じられることがあります。その命令に対する準抗告が可能です。
準抗告が棄却された時は、最高裁判所に対して「特別抗告」を申し立てることができますが(刑事訴訟法第433条1項)、憲法違反や判例違反といった理由も必要となり一段とハードルが上がります。
準抗告手続きの流れと弁護活動
圧倒的に多く申し立てをするのは、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判についてです。
勾留に関する裁判に対する準抗告
勾留とは、被疑者や被告人の身柄拘束のことを言います。勾留の裁判に対する準抗告では、勾留の要件を満たしていないことを裁判官に認めてもらう必要があります。では、どういった事情が勾留の要件を満たしていないことになるのでしょうか。
被疑者としての勾留を例として見てみましょう。
まず、逮捕されてしまった場合、検察官宛てに勾留請求回避のための意見書を提出したり、検察官による勾留請求後は、裁判官宛てに勾留請求却下のための意見書を提出したりするなどして、勾留決定を回避する弁護活動をします。それでも勾留決定してしまった場合に、そもそも勾留の要件を満たさないことを主張する準抗告や、勾留すべき理由や必要性がなくなったことを主張する勾留取消請求(刑事訴訟法第207条1項、第87条1項)を申し立てることになります。
すでに勾留決定がされた後のタイミングで弁護士に依頼する場合には、勾留決定に対する準抗告が勾留を回避するために残された手段となります。
勾留は人の行動の自由を長期間奪うという大きな制約を伴う強制処分であるにもかかわらず、日本では、「自動販売機」とも揶揄される程、裁判官が勾留決定をする確率は非常に高いのが現状です。
本当に勾留の要件を満たすのか、本当に当該事件の捜査のために被疑者の身柄を拘束するまでの必要性があるのか、ある意味弁護人が法の番人となって、裁判官の判断を正す役割を担う必要があります。勾留の要件は刑事訴訟法60条1項に定められています。
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
当然ではありますが、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」がまず大前提の要件で、これに加え、
- 定まった住居を有しないとき
- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれかに当たることが要件になっています。
この刑事訴訟法第60条1項に定められている勾留の要件は、一般的に「勾留の理由」と呼ばれています。さらに、勾留取消請求の条文である刑事訴訟法第87条1項をご覧ください。
刑事訴訟法第87条1項
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
この条文は、勾留の「理由」または「必要」がなくなったときは、勾留を取り消さなければならない旨規定するものですが、この条文により、そもそも勾留はその「必要」もあるからこそ認められるものだと考えられていることが分かります。
したがって、このことから、「勾留の必要性があること」も勾留の要件に含まれると一般的に解されています。
勾留の必要性とは、例えば、被疑者がたまたま日本に観光に来ていた外国人で定まった住居を有せず、上記①と③が勾留の理由になっているとしても、当面の間、当該被疑者を住まわせ出頭確保してくれるような確実な身柄引受人がある場合には、勾留の必要性まではないということになります。
また、事案が極めて軽微で被害者も処罰感情がそれほど強くないのに対し、被疑者が大病を患っている場合に被疑者の身柄拘束をすることは、勾留の理由があるとしても、相当性を欠くとして、勾留の必要性がないと考えられます。
多くの場合、勾留の必要性の判断要素、とりわけ被疑者側に有利に働く事情については、被疑者側からアピールしない限り、勾留の裁判をする裁判官や勾留決定に対する準抗告の申立ての判断をする裁判所の目に触れることはありません。したがって、ここにも、弁護人の大きな存在意義があります。
痴漢や盗撮等比較的軽微な犯罪の部類に属すると考えられている犯罪の被疑者については、検察官も被疑者に身元引受人となってくれる家族がいるか等被疑者に有利な事情があるかを検討して勾留請求をするかどうかの判断をすることがありますが、それ以外の一定程度重い犯罪ですと、検察官は当然のように勾留請求しますし、その際、わざわざ裁判官に対して被疑者に有利な事情を伝えることはしません。
裁判官に、より公正に勾留の判断をしてもらうためには、弁護人を通して、被疑者に有利な事情という追加の判断材料を提供する必要があるのです。
なお、勾留に関する裁判には、接見等禁止決定も含まれますので、接見等禁止決定に対しても準抗告をすることができます。
勾留決定と同時に接見等禁止決定がされた場合に、勾留決定に対する準抗告が奏功しなかったときには、勾留中の被疑者が少なくとも家族や友人等と面会できるよう、接見等禁止決定に対する準抗告の申立てをすることが考えられます。
保釈に関する裁判に対する準抗告
保釈とは、起訴後に勾留の効果の存続を前提としながら、保釈保証金の納付等を条件に、被告人の身柄を解放する決定のことをいいます。
弁護人が、被告人の保釈請求をし、裁判所がこれを却下する決定を行った場合には、勾留決定に対する準抗告の際と同様に、弁護人は保釈の要件を満たすことを主張して、保釈請求の却下決定に対する準抗告の申立てを行うことができます。逆に、裁判所が保釈を許可する決定をした場合には、検察官が準抗告の申立てをすることができます。
検察官から準抗告の申立てがされた場合には、被告人は準抗告の判断が出るまで釈放されません。検察官が当初より保釈について反対の意見を持っていることが分かっている場合には保釈許可決定後、準抗告の申立て予定があるか、検察官に確認するのがよいでしょう。
押収又は押収物の還付に関する裁判に対する準抗告
「押収」とは、捜査機関による差押えや領置、裁判所による差押えや領置、提出命令のことをいいますが、実務上、裁判所による押収はまれです。
また、捜査機関が差し押さえをする場合、通常、裁判所から発付された捜索差押許可状に基づいて行われ、差押行為一つ一つにつき裁判所がそれを認める裁判を行うわけではありません。
したがって、捜査機関による差押処分に不服がある場合には、刑事訴訟法第430条に基づき、捜査機関のした差押処分の取消しを求める準抗告の申立てを裁判所に対してすることになります。その場合、差押えられた物が明らかに被疑事実とは関係ないものであることや、捜索差押許可状に差し押えるべき物として記載のない物である等の主張をしていくこととなるでしょう。
また、押収物の還付請求に対し、捜査機関が応じない場合や還付請求却下処分をした場合にも、刑事訴訟法第430条に基づき、裁判所に対して準抗告の申立てをすることができます。なお、捜査機関の請求によって裁判官が行った差押許可状の発付の裁判そのものに不服がある場合には、刑事訴訟法第429条1項2号に基づいて裁判所に対して準抗告の申立てをすることも考えられますが、この場合、差押処分前にする必要があり、差押処分がなされた後の場合は、裁判の効力が消滅しており申立ての利益がないとされています。
準抗告の認容と確率
申立てをしてからどのくらいの期間で結果が出るかという点ですが、基本的には、申立てをしたその日、もしくは翌日に結果が出ることとなります。前述した特別抗告をする場合には、準抗告の棄却決定が出てから5日以内に申し立てる必要があります(刑事訴訟法第433条2項)。
勾留決定に対する準抗告が認容された場合には、認容された当日に身柄が解放されます。
2013年は、準抗告申立て9,438件に対し、認容は1,512件で、16%の認容率でしたが、2018年は、準抗告申立13,263件に対し、認容は2,541件で、19%の認容率と認容率が上がっています(弁護士白書2019年年版)。準抗告申立ての件数の増加は、裁判官らに対して勾留の決定等をより慎重にすべき旨警笛を鳴らす役割もしているといえるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。勾留は、人の行動の自由を奪うという大きな制約を伴う強制処分であるにもかかわらず、裁判官の多くは抽象的な逃亡や罪証隠滅のおそれを理由に、当然のごとく検察官による勾留請求を認める「自動販売機」になりがちです。
もちろん、事案によっては、勾留を避けられないケースもありますが、まずは、準抗告認容が望める事案なのか、望めないとしても他に早期身柄解放のためにできることはないか、弁護士にご相談ください。